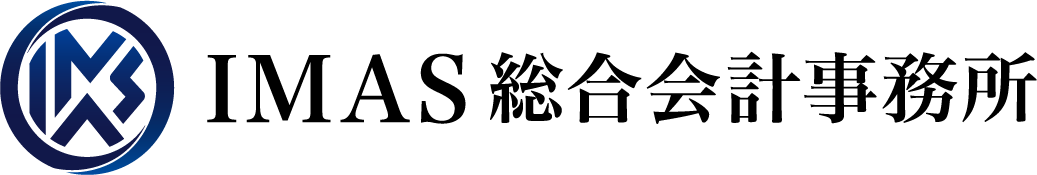価格改定の進め方(中小企業向け)──利益を守るための5ステップ

原価上昇・人件費・物流費…コストは待ってくれません。
それでも「値上げ=離反が怖い」で先送りすると、粗利は確実に痩せます。
本記事では、ムリ・ムラのない価格改定を実行するための実務プロセスと、社外通知テンプレ・現場FAQまで“そのまま使える形”でまとめました。
STEP1:データで根拠づくり(採算と影響度)
感覚値での値上げは反発を招きます。まずは「現状採算」と「値上げの影響」を数値で見える化します。
1-1. 顧客×商品(サービス)採算
次の視点で「赤字/薄利」を抽出します。
- 粗利率(=(売上−変動費)/売上)
- 1件あたり粗利額
- 提供工数/配送コスト/在庫回転/クレーム頻度
| 顧客 | 商品 | 売上 | 変動費 | 粗利率 | 工数/配送 | 採算評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A社 | スタンダード | 1,000,000 | 720,000 | 28% | 標準 | △(要改定) |
| B社 | カスタム | 1,500,000 | 1,020,000 | 32% | 高負荷 | ×(赤字懸念) |
1-2. 影響度(価格弾力性・離反リスク)
過去の改定/競合/代替可能性から「値上げ許容幅」を仮置きします。
- 高付加価値・代替困難:+5〜10%以上でも可
- 汎用品・価格比較が容易:+3〜5%を複数回に分ける
1-3. “最低限守る粗利率”の設定
例:最低35%。ここを割る取引は「条件見直し or 価格改定」の対象に。
STEP2:改定設計(対象・幅・方式)
一律値上げよりも、実態に合わせた“組み合わせ”が有効です。
2-1. 方式の選択肢
- 定価改定:リスト価格自体を見直し
- サーチャージ:原材料・燃料・為替の変動分を連動式で転嫁
- プラン化:上位プラン新設、標準機能の整理、オプション外出し
- 最低発注/最低料金:小口・スポットの採算確保
- 納期/品質差別:短納期・特急は別料金
2-2. 値上げ幅のたたき台(例)
| 対象 | 現在粗利率 | 目標粗利率 | 必要改定幅の目安 |
|---|---|---|---|
| 赤字顧客(全商品) | <25% | 35% | +10〜15% |
| 高負荷品/特注 | 25〜30% | 40% | +8〜12% |
| 汎用・競合多 | 30〜35% | 35〜38% | +3〜5% |
STEP3:顧客セグメント別シナリオ
- A:戦略顧客……段階改定・長期契約化・上位プラン提案
- B:標準顧客……定価改定+サーチャージ、FAQで理解促進
- C:採算悪化……最低料金/ロット・納期条件変更・値上げ交渉
※代替提案(仕様簡素化・納期延長・数量取りまとめ)を同時に出すと交渉がスムーズ。
STEP4:社内合意・FAQ整備
- 価格表・割引権限・例外条件の定義(個別裁量は最小に)
- 営業向け“想定問答集(Objection Handling)”の共有
- 受注・請求・システム(在庫/品番/プラン)の同期
現場向け:想定問答(抜粋)
- Q. なぜ今値上げ? ─ 「原材料・物流・人件費の高騰が継続し、品質維持のため見直しが必要です。仕様の見直しをご一緒に検討すれば、上昇幅を抑える選択肢もご提案できます。」
- Q. 他社は値上げしていない ─ 「弊社は◯◯(品質・安定供給・サポート)を維持しています。直近12か月の◯◯指標も改善。価格だけの比較ではなく、総コストでご判断ください。」
- Q. 値上げは困る ─ 「たとえば発注単位の見直し・納期延長・仕様簡素化なら価格上昇を最小化できます。」
STEP5:通知・交渉・実施後フォロー
5-1. タイムライン(目安)
- 60〜45日前:取引基本方針の事前共有(キーマンへ口頭)
- 45〜30日前:文書通知(メール+書面)・代替提案提示
- 実施日:基幹マスタ切替/請求単価反映
- 翌月:解約率・粗利率・クレーム件数・代替採用率をモニタリング
5-2. モニタリングKPI(ダッシュボード反映)
- 粗利率(当月/対象顧客/対象商品)
- 受注見込(今月・来月)・案件ステージ
- 解約率・リピート率・値引き要望率
- 顧客別粗利トップ/ボトム10
価格改定・案内文テンプレ(そのまま利用可)
取引先向け通知メール/書面(例)
件名:価格改定のご案内(◯年◯月◯日以降のご注文分)
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨今の原材料・物流費・人件費の上昇が継続する中、品質・安定供給の維持のため、下記の通り価格を改定させていただきます。
- 対象商品/サービス:◯◯
- 改定内容:現行価格の +◯%(新価格:◯◯円〜)
- 適用開始日:◯年◯月◯日
仕様の見直しや数量取りまとめ等により、お客様のご負担を最小化する提案も可能です。
ご不明点がございましたら担当までお問い合わせください。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
実行チェックリスト
- 最低粗利率・対象顧客・対象商品を定義した
- 値上げ幅・方式(定価/サーチャージ/プラン)を決定した
- 営業権限・例外ルール・FAQを整備した
- 通知文を準備し、実施日・切替手順を社内共有した
- KPI(粗利率/解約率/受注見込)の監視枠をダッシュボードに追加した
よくある質問
どのくらいの頻度で改定すべき?
年1回の“まとめて改定”より、四半期・半期の“こまめな見直し”の方が顧客負担・反発ともに抑えやすい傾向があります。サーチャージ連動も有効です。
値上げで解約されたら?
解約率・粗利のトレードオフを事前に試算しましょう。低粗利のゾーンでの解約は、全体利益の改善につながるケースも多いです。代替提案を必ずセットで提示します。
既存長期契約はどう扱う?
契約更改時の見直しが原則。長期固定の対価として、年次サーチャージ連動・プランアップ・最低数量など条件の組合せで合意を取りに行きます。