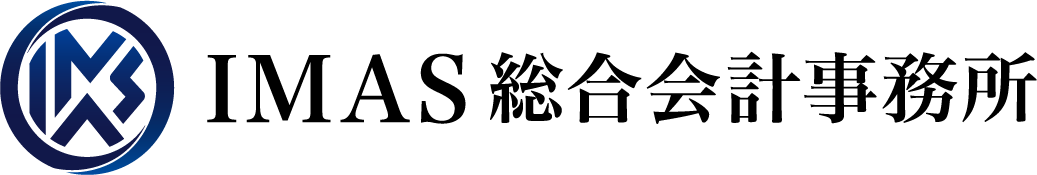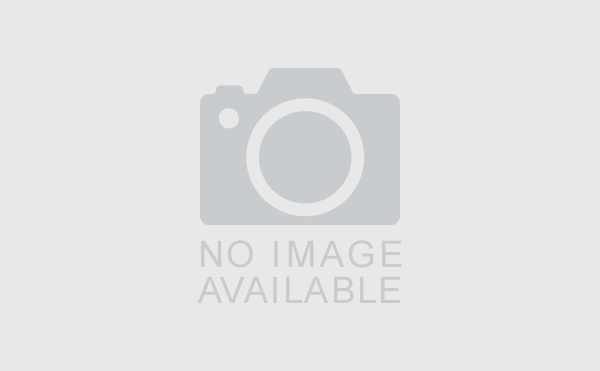中小企業がやりがちな節税の落とし穴トップ5

「節税=コスト削減」だけに捉われると、翌期の資金繰りや税務リスクを招きがちです。
よくある5つの落とし穴と、すぐ実践できる対策を整理しました。
- 典型的な節税の失敗パターン
- 税務調査で指摘されやすい論点
- キャッシュを守るためのアクション
落とし穴1:期末に“駆け込み支出”を積み上げる
期末に必要性の薄い経費を増やすと、翌期のキャッシュ不足・生産性低下を招きます。
税務上は合理性が重視され、用途が曖昧な支出は否認リスクも。
対策:投資回収の見込みを数値化(効果・時期)し、稟議とエビデンスを残す。来期予算と整合させる。
落とし穴2:交際費/会議費の区分が曖昧
参加者・目的の記録がなく摘要が「会食」だけ…は指摘の温床。交際費等の損金算入枠も考慮が必要です。
社内飲食を会議費にする場合も、議題・資料・出席者のメモが必須。
対策:精算時に「社内/社外・人数・議題」を必須入力。経費規程に線引きを明文化し、承認ルートを固定。
落とし穴3:修繕費と資本的支出の区別ミス
性能向上や耐用年数の延長は資本的支出として資産計上が原則。修繕費で一括損金にすると否認リスク。
金額基準と内容基準の両方で判定を。
対策:見積・請求・仕様書で「原状回復か性能向上か」を明示。判定メモを固定資産台帳と一緒に保存。
落とし穴4:少額資産の判定
少額減価償却資産等の判定で耳にしたことがある金額の基準は10万円未満・20万円未満・30万円未満ではないでしょうか。実際には細かい判定基準がこれ以外にも存在しますが、償却資産税(固定資産税)の取り扱いは違うなど、抑えるべきポイントは実は意外と多いです。
対策:金額基準・耐用年数の社内ルールを明文化。会計ソフトの科目ルールを定期棚卸し。
落とし穴5:役員関連取引(貸付金・社宅・立替)の放置
役員貸付金・役員個人立替・社宅の賃料設定などは、同族会社ゆえの論点で要注意。
実態と書面(契約・議事録・返済計画)が一致していないと、否認や給与課税リスクに発展します。
あたりまえのようで混同されていることが多いのが、役員と会社はまったくの別人格ということ。
対策:契約書・返済スケジュール・議事録を整備。相殺・清算の工程を月次でチェック。
今日からできるチェックリスト
よくある質問(FAQ)
Q1. 節税のために期末にまとめ買いは有効?
翌期のキャッシュ圧迫や遊休資産化のリスクが高いです。投資回収の見通しが立つ支出に絞りましょう。
Q2. 少額資産の基準は毎期変えてもよい?
原則は資産ごとに判定し、その単位で機能が発揮できるかどうかという基準で考えます。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務判断を示すものではありません。
実際の適用にあたっては、必ず税理士等の専門家にご相談ください。